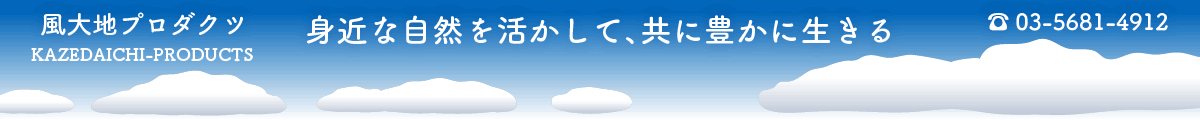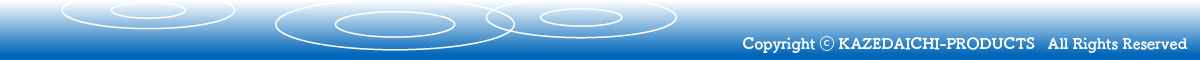設置場所に合う寸法・雨水活用システムに、自由設計できる



“雨びつ”は、国産杉の間伐材を積上げた構造体の中に、防水袋を納めて配管するつくりの特注雨水タンクです。なので、設置場所と雨水活用の目的に合わせて設計できる自由があります。大きさ・形・連結の自由、配管の自由、組み入れるシステムの自由、…例えば、雨水のポンプアップ、散水・灌水システムへのジョイント、貯水量の検知、水道水の自動補給、自然循環方式、など。そしてさらに、外観もナチュラルでカッコいいのです。容量は、350ℓ以上、1000ℓ超も。
 “雨びつ”で、雨水はこのように活用できる
“雨びつ”で、雨水はこのように活用できる
緑化・涼しさづくりを雨水活用で

↑この事例では、雨びつを既存の灌水システムにつないで、雨水と水道水で水やりしています。雨が足りない時は、水道水を雨びつの中に自動的に補給します。自動灌水で、夏はゴーヤなどを育て、緑のカーテンによる涼しさづくりを行っています。
(都立木場公園ミドリアム様)
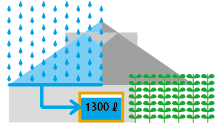
↑屋根から雨水を集める
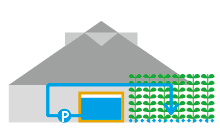
↑雨水をポンプで送り、植物に水やり
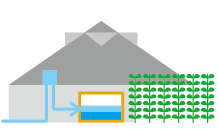
↑雨水が足りない時は、水道水を補給
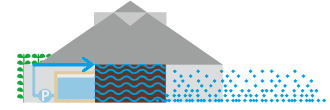
↑打ち水や蒸発冷却の壁で、クールスポットづくり
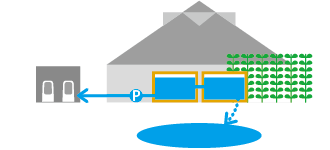
↑ビオトープに雨水を補給して、滞留を防ぐ
↑災害トイレの洗浄水にも

↑雨びつに無電源の安藤式自動灌水装置をつないで、花で出迎え(葛飾区役所様)

↑手押しポンプで、中庭の花園に(都立武蔵野北高校様)

←木の断熱性能の良さで屋上貯留槽に。 特製ろ過装置で、洗濯水に利用(世田谷区H様)
いざという時に、すぐ使える水源
雨びつなど地上設置型の雨水タンクは、水量は小さいものの、すぐそこにあって手が届く水源です。災害時、電気が止まっても使うことができ、圧送手押しポンプなら3階まで送水することができます。水道水のほかに、二次水源としてご活用ください。
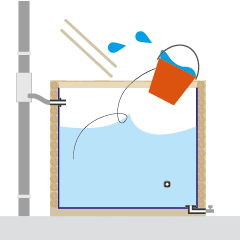
↑バケツで汲み上げる
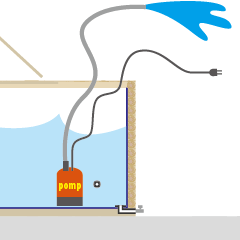
↑ハンディポンプで汲み上げる
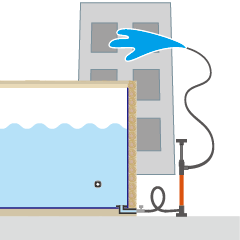
↑圧送手押しポンプなら、3階まで揚がる
 えっ、天然の木でできてるの? …水漏れない? 腐らない?
えっ、天然の木でできてるの? …水漏れない? 腐らない?
雨びつは、木だからできる、特注の雨水タンクです。
設置場所と雨水活用の目的に合わせて、大きさ、形、連結、配管、組み入れるシステムが自由設計できます。
角材を積上げた構造体に、防水袋を内装するつくりなので、木材の乾燥収縮による水漏れの心配はありません。

↑現地で角材を組み上げる

↑防水袋を内装する

↑配管する
木製の雨水タンク “雨びつ”のメリット
-
 自由設計できる。…大きさ、形、連結、配管、組み入れるシステムなど
自由設計できる。…大きさ、形、連結、配管、組み入れるシステムなど -
 木は断熱性が高いので、夏場の水温上昇が抑えられて水質が安定する。
木は断熱性が高いので、夏場の水温上昇が抑えられて水質が安定する。 -
 塗装で着色もできて、リニューアルも利く。
塗装で着色もできて、リニューアルも利く。 -
 焼却しても有毒ガスが出ない。木屑として廃棄できるので、最後の処分が楽。
焼却しても有毒ガスが出ない。木屑として廃棄できるので、最後の処分が楽。 -
…
-
 さらに、格好よくて景観と調和する。
さらに、格好よくて景観と調和する。 -
 おまけに、日本の杉の間伐材を使って、森林整備と二酸化炭素の固定に役立つ。
おまけに、日本の杉の間伐材を使って、森林整備と二酸化炭素の固定に役立つ。
国産杉の間伐材を、長寿命加工
天然木そのままで屋外に設置したら、4〜5年で腐るでしょう。
でも、雨びつは、加圧注入プラントで、AQ認証レベルの高度な防腐処理をしていますので、無処理材の3~4倍も長持ちします。
薬剤には、無色透明のモクボーAACという植物由来の防腐剤を使っています。
シックハウスの原因となるVOC関連の規制物質は使用していません。

←加圧注入プラントで木材の奥まで防腐処理するので、長寿命
※AQ認証は、(財)日本住宅木材技術センターが実施している、木質建材の質・性能を保証する制度です。
 “雨びつ”の基本仕様と自由設計の例
“雨びつ”の基本仕様と自由設計の例
“雨びつ”の基本仕様
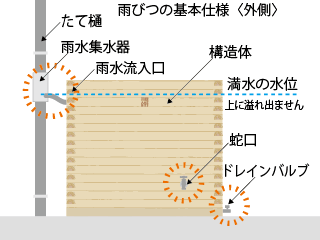
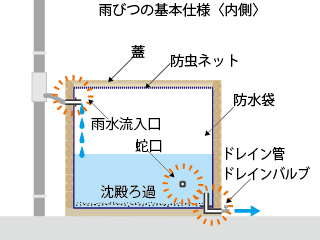
雨水の出入口は、基本仕様では3ヶ所 … 雨水流入口・蛇口・ドレイン。
出入口の取り付け位置は、変更することができます。
“雨びつ”の容量と外寸の目安 継手類を除く、構造体の寸法
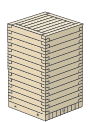
350ℓ
740×740×H1260mm
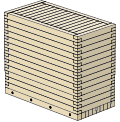
800ℓ
1490×740×H1260mm
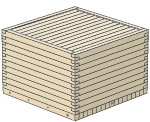
1300ℓ
1490×1490×H990mm
上記のほかに、設置する場所に合わせた寸法で作ることができます。
ただし、木材の長さは3mまたは4mなので、木取りによっては割高になることがあります。ご相談ください。
“雨びつ”の自由設計の例
物理的な機能を加える。
・電動ポンプで送水する。
・水道水を自動補給する。
・沈殿槽、ろ過層を設ける。

↑電動ポンプ、流量計

↑水道水補給、水位計
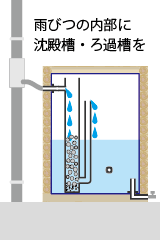
↑内蔵ろ過装置

↑外付けろ過装置
アメニティを求める。
・景観との調和。
・エコなハイブリッド化。
・雨水循環モニュメント。
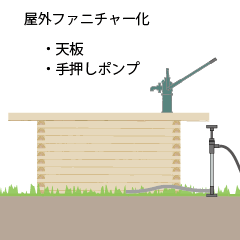
↑身近な二次水源に
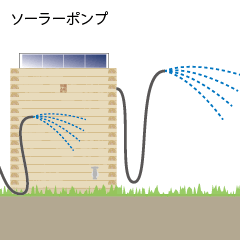
↑タイマーセットで自動灌水も

↑集水テントの櫓つき
「うっかり腐り水」を防ぐ“自然循環方式”にも
水(H2O)自体は腐りませんが、有機物や微生物が増えて濁りや臭いを発生させると「水が腐った」と言います。貯めた雨水を日頃から使って水を循環させていれば問題はないのですが、うっかり貯めっ放して滞留が続くと腐りやすくなります。
この「うっかり腐り水」を防ぐために、雨びつにオーバーフロー機能を加えて、“自然循環方式”に変えることもできます。雨が降る度に貯めた雨水が入れ替わるので、滞留を防ぎます。
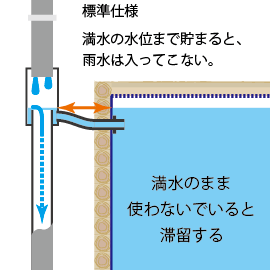
↑シンプルな配管の標準仕様
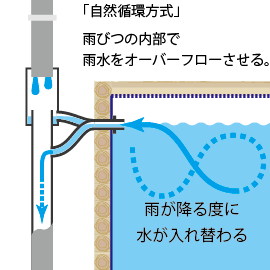
↑オーバーフロー管を設けて「自然循環方式」に
 たて樋から雨水を集める …雨水集水装置について
たて樋から雨水を集める …雨水集水装置について
雨水を集めるために、建物のたて樋を途中で切断して、雨水集水装置を取り付けます。
雨水集水装置は、取り付けるたて樋と用途に合わせて選定します。
雨水集水装置と雨びつは、ホースまたは塩ビ管などで接続します。
ほとんどの雨水集水装置にオーバーフロー機能があるので、
雨びつの標準仕様ではオーバーフロー管を設けていません。
 |
〈標準装備品〉マイホームライト(ポリエチレン製) 適合するたて樋 丸樋 φ55・φ60・φ76mm、角樋の一部 ごみ取り皿付き、色はグリーン・グレー・くろ |
|---|---|
 |
〈オプション〉マイホームライト75(ポリエチレン製) 適合するたて樋 VP/VU75 ごみ取り皿付き、色はグリーン・グレー |
 |
〈オプション〉サンエーコレクター(塩ビ製) 適合するたて樋 VP/VU75・100・125・150 塩ビ管の直結が可能 |
 |
〈オプション〉ウィジーコレクター(ステンレス製) 適合するたて樋 丸樋 φ60・φ76mm、VP/VU75・100・125 メッシュフィルター付き 並目:庭の散水が目的で、器機に接続しない場合はこちら 細目:電動ポンプなど器機に接続する場合はこちら |
雨水集水装置と“雨びつ”の関係
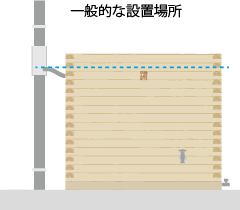
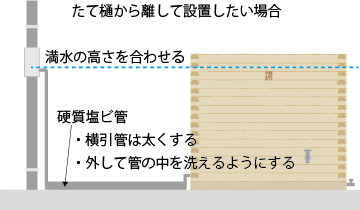
雨水タンクはたて樋のすぐ近くに設置することが一般的ですが、条件を整えれば、たて樋から離して設置することもできます。特に、横引管には沈殿物が溜まりやすいので、太くして詰まりにくくすること、中を清掃できるように取り外せる構造にしておくこと、が大切です。
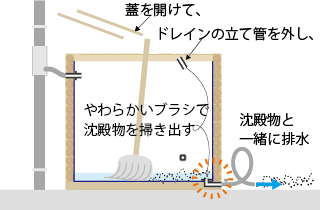
雨水集水装置の内部のゴミや、雨びつの沈殿物の溜まり具合は、設置場所の環境、雨水集水装置のフィルターの種類などによって大きく異なります。様子を見ながら、適宜清掃をしてください。
 無電源の自動灌水装置をつないで、緑のカーテンを楽に育てよう
無電源の自動灌水装置をつないで、緑のカーテンを楽に育てよう
貯めた雨水を植物に与えると、植物の蒸散を通して雨水は再び天に戻ります。その蒸発冷却による涼しさづくりの一つが緑のカーテンです。
雨びつに電気も要らない“安藤式自動灌水装置”をつないで、緑のカーテンを楽に育ててみませんか?

↑安藤式自動灌水装置:底から給水タイプ
土を使うプランター栽培のほか、土要らずの水耕栽培もできます。
一般的な自動灌水装置は、水道の圧力で作動するため、雨水タンクの低水圧では働きません。一方、“安藤式自動灌水装置”は、水位差0〜1500mmの低水圧で作動する自動灌水装置で、電力を使わずに、プランター底部の水位を維持し補給します。
夏場に多量の給水が必要な緑のカーテンなど、水やりの手間が大いに省けます。

↑安藤式自動灌水装置で水耕栽培した緑のカーテン。土要らずなので、集合住宅やオフィスでも楽にできる。
![]() 詳しいご案内は、「安藤式自動灌水装置」(PDF)でご覧ください。
詳しいご案内は、「安藤式自動灌水装置」(PDF)でご覧ください。
 “雨びつ”の価格とオプション一覧
“雨びつ”の価格とオプション一覧
![]() こちらの「雨びつの主な仕様と価格」(PDF)をご覧ください。
こちらの「雨びつの主な仕様と価格」(PDF)をご覧ください。
“雨びつ”のお問合せ・ご注文はこちら
 お問合せフォームはこちら
お問合せフォームはこちら
上記のほかにも
Eメールで、
FAX(03-5681-4911)で、
電話(03-5681-4912)で、お問い合わせください。
電話の場合は、つながりにくいことがあります。
折り返しご連絡いたしますので、お客様のお名前と連絡先、ご用件をお伝えください。